久々にBlenderを使ってみようと思いインストール。
数日前の記事でもBlenderの件を書いた。
何度目の挑戦だろう
Blenderを使ってみようと思いMacにインストールした。
バージョンは2.90.1で見た目はだいぶ今まで使ってきた3DCGアプリっぽくなっている。
何度も挫折しているBlenderをインストールした理由は
- Apple Motionで使えるDSMZ形式への3Dモデルデータ変換ができる。
- 以前から気になっていた流体系の簡易シミュレーション機能が搭載されている。
- GPUレンダリングがMacでも使えるらしい。
という、大した理由ではない。
流体系の簡易シミュレーションを使ってみた。
仕事ではエアフロー解析で本格的な流体解析を使っている。
でも、3DCGアプリの出力と異なり圧力や速度または流量などの数値データをコンタ図で
表示して設計の妥当性を確認する事が主な使い方なのでビジュアル的には地味だ。
なので、Blenderで流体系の簡易シミュレーション機能で見た目がそれっぽい動画を
作ってみたいなって思うんだよね。
なので下調べもせず使ってみた。
ぱっと見わかりにくいメニュー構成だけど
シミュレーション機能のメニューは今まで使ってきた3DCGアプリと大差ない。
エアフロー解析と似たような設定もある。
ってことで、試行錯誤はしたけど自分で設定しシミュレーション機能を使えた。
悩む事は文言の違いでエアフロー解析では計算領域って言われる計算する範囲の事を
Domainって表現されている。
他のアプリではcontaって表現されている物もあるよね。

最初は、よく使うパーティクルを飛ばして煙のボリュームシェーダーを付加する方法で
煙を表現しようとしたんだけど直線的な動きになり違和感があったので
Fluid機能のSmokeを使って煙を作った。
エアフロー解析と違い3DCGアプリの流体系の簡易シミュレーション機能は流体そのものに
速度を加えるとこが大きく違うよね。
エアフロー解析では外力としてファンや動作する物体を配置してそれらの作用で気体を
移動させるのでより実世界に近い解析ができるのが良いとこだと思う。

GPUレンダリングを選択できず悩んでしまった。
BlenderはGPUレンダリングができるって思い込んでいた。
だが、最新版のMacOSやBig SurではOpen-CLもCUDAも非対応なのでMetal対応アプリしか
GPUレンダリングができない。
なので、素のMac版BlenderはGPUレンダリングができない。
何か代替手段があるのかなと調べたらRadeon用のGPUレンダリング機能がGitHubで開発され
配布されていた。
RadeonProRenderというアドインで無料配布している。
っで、最新版を入れるとムッチャ不安定。
View Port表示は安定しているけどレンダリングすると即Blenderがクラッシュ。
設定をいろいろいじったけどダメ。
数種類のバージョンを使ってみたBig Sur環境のMac版Blender2.90.1で安定して動くのは
バージョン2.5.1だと言うことがわかった。

Vew PortもレンダリングもGPUレンダリングで安定していて問題無く動いている。

だが、自分で解決できていない問題もある。
なぜか材料をガラスに指定してレンダリングすると
屈折率をどんな値に変更してもガラスの向こう側の煙がレンダリングされない。
これは仕様なのかバグなのか・・・

とりあえず、
ちまちまとBlenderの使い方を学習していこうと思う。
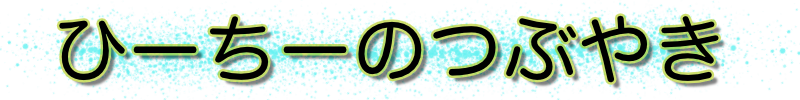




コメント